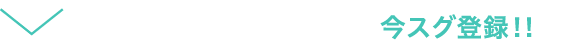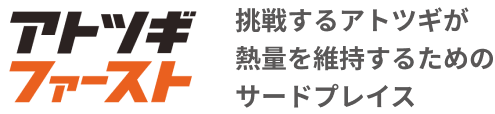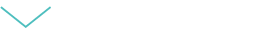自律的チームプレーで一生使える包丁文化を創出する
一文字厨器株式会社
代表取締役 田中 諒 氏
世界一の品ぞろえとメンテナンスで、第一線で活躍するシェフや板前の一流の味を支えている包丁ブランド「堺一文字光秀」。3代目の田中諒氏は創業者である祖父の思いをつなぎたいと考え、自らの意思で家業を継ぐことを決めた。広告業界で身につけた合理的なマーケティング手法でもない、会社にもともとあった個人商店の集合体でもない、それぞれの個性を生かしながら泥臭いチームプレーの風土を育み、料理がしたくなる、包丁が使いたくなる文化の創出を図っていこうとしている。

自分の意思で事業を継ぎたいと思えた
Q 一文字厨器の事業内容は
A 大阪の道具屋筋商店街で包丁を売ってきました
祖父が1953年に大阪・難波の千日前道具屋筋商店街で包丁店を始めました。道具屋筋商店街は、プロの料理人の目利きにかなった道具で食の文化を支える店が軒を連ねており、東京の合羽橋商店街と並ぶ、世界でも稀有な料理人のための商店街です。そのなかで当社は世界でも最も多いであろう2千種類を超える包丁をそろえ、売るだけでなく、使い方のサポート、包丁研ぎをはじめとするメンテナンスまでを行い、料理人を支えてきました。

Q 家業を継ごうと思ったきっかけは
A 祖父の思いをつなぎたいと思ったんです
ぼくが高校2年生の時に祖父が亡くなりました。近しい人が亡くなった初めての体験で、葬式の間、あの優しい祖父がいなくなってしまったことが信じられず、放心状態でした。祖父は周囲の方々から尊敬を集めており、亡くなった後も店には祖父がいるような気がしました。

好きなことを仕事にという風潮があったので、ミュージシャンになりたいと思っていましたが、創業者である祖父の思いをつなげるチャンスがあるなら、ぼくが継ぎたいと思うようになりました。それまで、あとを継いでほしいと言われたことは一度もありませんでした。やらされてやるのではなく、自分の意思で会社を継げたことはありがたいと思っています。
一人ひとりの価値観を尊重する社風へ
Q 入社してどのようなことを感じたか
A 遅れた世界を自分がすべて変えてやろうと決意
大学卒業後は、「思いをつなげる」の最前線の市場に身を置きたいと考え、SNSやスマートフォン黎明期のWEB広告の会社に入社しました。最良の提案を行うためにあらゆるデータを可視化してそれらを駆使し、PDCAを回しながら改善を重ねていくという仕事のやり方でした。そこで10年ほど働き、すっかりその感覚に染まった私にとって、家業はなんと時代に取り残された世界なんだろうと感じました。

足りない包丁を仕入れて並べ、買ってくれる人がいて、その結果マイナスよりプラスが大きいと利益が出て良かったね、という世界です。すでにネット販売は始めていましたが、経理の人にネットの売上を尋ねたらそろばんで計算をし始めた時は衝撃でした。仕事観が揺るがされ、この遅れた世界を自分が全部変えてやるという気持ちになりました。
Q 順調に進んだのでしょうか
A 若手社員が辞めたことをきっかけに、価値観の押し付けをやめた
若い社員が入社してくれたのですが、精神的なダメージで会社に来なくなってしまったんです。理由の一つは、ぼくの指示とベテラン社員の指示が真逆で、その板挟みになっていたことです。彼は文句ひとつ言わずがんばってくれていました。その経験を通して、自分の中のOSが、前職のような合理的な組織型でもなく、今のような個人商店の集合型でもない、柔軟なOSに切り替わりました。

新規事業、DX、マーケティングなどアトツギの世界でやるべきこととされている一連の取り組みによって一時的に会社は良くなるかもしれませんが、一人ひとりの社員は自分の責任でお客さんと向き合い、包丁が売れることにやりがいを感じています。どちらかの価値観を押し付けようとすると対立構造が生まれます。そうではなく、現状と将来の会社の姿を並べた上で、それぞれの社員さんの目線になって想像力を働かせて会話をするように心がけています。ただ、一方で社員さんの気持ちをわかったつもりにはならないようにすることも大切だと考えています。みんな一生懸命に働いている中、どうしても景色が違うわけなので、「わかり続けようとする姿勢」みたいなものを持ち続けられれば良いなと思っています。

Q お父様との関係は
A 自由にやらせてくれていることに感謝しています。
父は自分のやろうとすることを自由にやらせてくれています。今もレジは締めてくれています。2022年3月に社長に就任しましたが、かつて祖父が会長を退き、父が社長になったのと同じ年齢で、ぼくに引き継ごうと考えていたようです。祖父は3つの会社を作り、それを3人の息子に1社ずつ継がせ、相続税も現金で用意するような人でした。父も祖父の姿を見て、きれいに引き継ごうと考えてくれたのだと思います。

社会の変化に合わせ包丁を使う文化を起こしていく
Q 今、力を入れて取り組んでいることは
A 料理文化が広がるための根っこをつくっていきたい
2013年には和食がユネスコ世界文化遺産に登録され、2020年には人口当たりのミシュランの星の数は日本が世界一になりました。これだけ食文化が発達した国を道具で支えてきたという価値はますます高まっています。しかし、プロの中でも限られた方だけがその価値に気づいてくださってはいるものの、国内の風潮としてはとにかく安いもので道具を揃えようという考え方が主流になりつつあります。ご家庭では約6割の方が100円均一や安い雑貨店で包丁を購入し、6割の方が包丁を研いでいないというデータがあります。安い包丁を買って捨ててはまた新しい包丁を買い直す人がほとんどではないでしょうか。料理をしたい、包丁が使いたいと思えるきっかけづくりとともに、一生使える包丁を大事に使う文化を広めていきたいと考えています。

そこで現在、店の2階のスペースを活用した「一十一(いちとい)プロジェクト」を動かそうとしています。「一十一」は屋号の一文字と十一(問い)をつなぎ合わせ、一文字が社会に問いかけをし、日本の食文化、道具文化を作り、広げ、守っていこうとする取り組みです。テストキッチン、イベントができるスペースも設け、作り手、使い手、行政、教育機関、商店街、マスコミなども巻き込み、料理文化自体が広がる根っこを作っていきたいと考えています。
Q 「一十一(いちとい)プロジェクト」への期待は
A 社内外で新しい文化を育む場にしていきたい
包丁の価値が高まったことで、世界中の人が包丁を買いに来てくれることはありがたいことですが、そこに目を向けた事業者が次々に参入しています。認知されることはよいことですが、にわか仕込みでもたくさん売れることで、作り手の供給も表面的なニーズに合わせざるを得なくなる。日本の包丁は長く使えるように作られていたことが強みだと考えているのですが、使い手のサポートやメンテナンスを伴わない供給が増えることで品質に対する信頼が揺らぎ、ブームに終わってしまうことを危惧しています。包丁を作る職人さんも減ってきています。「一十一(いちとい)プロジェクト」に集まってくる人たちの意見や思いを融合させながら、職人の育成、情報発信、商品開発などを進めていければと考えています。

社会に文化を起こそうというこのプロジェクトには、社員が自立的にチーム組んで、一人ひとりの文化に対する志を共有し、話し合いながら進めてもらっています。その中から私が考えも及ばないようなイベントを企画が生まれたりもしていて、自分で考え、行動を起こす組織ができあがりつつある手ごたえも感じています。個人の考えを尊重しながらも皆で泥臭くプロジェクトを進めていくやり方がうちには合っているのだと実感できるきっかけにもなりました。

アトツギ仲間と出会い、考え方が変わる
Q 未来志向のアトツギが集うコミュニティ「アトツギファースト」参加で得たもの
A アトツギファーストに出会ったからこそ今がある
2017年に中小機構のメルマガでOIH(大阪イノベーションハブ)のことを知り、そのイベントに参加するうちに事務局、アトツギの人とのネットワークができていきました。そこでの出会いや対話の中から、自立型の組織をつくるきっかけができ、歴史や哲学に触れ、家業のことを深く考えるきっかけにもなりました。

例えば、PDCAを回すのでも、社員にいきなりDCAをやらされるのでは誰もやる気が出ないということにアトツギファーストのカレッジを通して気づき、Pから関わってもらうことで、主体的に考えワクワクしながら取り組んで貰えている気がします。また、歴史や哲学に触れることで、長い歴史の中で残されてきた言葉の大切さに気付き、職人さんや古くからの社員の思いや言葉に敬意を払うことができるようになりました。アトツギファーストのメンバーとのコラボ商品も生まれています。
Q アトツギにメッセージを
A 一緒に日本を面白くしていきましょう
同じ境遇のアトツギの人たちと接していると、お互い刺激し合って学び合えることばかりで、それ自体がエキサイティングです。その対話の中から日本に地殻変動を起こすような大きな話から、会社の組織を良くしていったり、新しい商品を開発するような施策のところまでさまざまなアイデアや考えが生み出され、やりがいを感じています。ぜひ一緒にいろいろなことを企んでいきましょう。

(文・山口裕史)